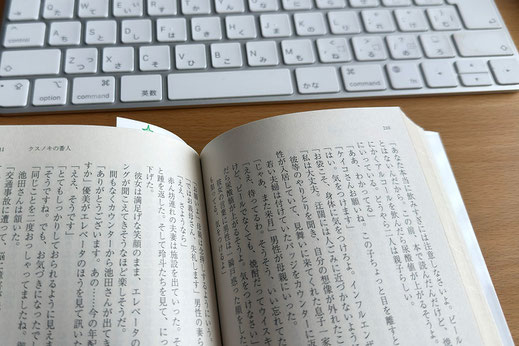
気がつけば、しばらく本を読んでいない。
そう思ったのは、SNSやブログ、ネットニュースなど、毎日たくさんの文章を読んでいるから「それで十分」と自分に言い聞かせていた時でした。
ところがある日、一日の時間を細かく区切ってみると「30分くらいなら本を読む時間が作れるのでは」と気づいたのです。
そこで東野圭吾の小説『クスノキの番人』を買ってみました。全480ページ、31章に分かれていて、ちょうど1章を読むのに30分ほど。
1日1章読めば約1か月で読み終えられる計算です。無理もなく、今のところ続けられています。
久しぶりに小説を読むと、意外に「読めない漢字」があることに気づきました。若い頃は雰囲気で読み飛ばしていましたが、今はそうはいきません。
知らないままにするのが気になり、スマホで写真を撮ってテキスト化し、「調べる」で読み方を表示しています。
そんな作業を繰り返すうちに、小説はやはり「言葉を教えてくれる存在」だと感じました。
一方で、Netflixも毎日時間を決めて楽しんでいます。ところが会話のシーンになると聞き取りづらいことがあり、日本語字幕を表示するようになりました。
すると、ここでも難しい漢字や表現に出会います。ルビがあるので読めはするのですが、どうしても文字を追ってしまう。
結果として、小説と同じように「言葉に触れる時間」になっているのです。吹き替え版でも日本語字幕を入れると、日本語の奥深さを再発見する良いきっかけになります。
日本語は本当に面白い。同じ「はし」という音でも、川を渡る「橋」と食事に使う「箸」では意味が全く違います。文脈によって意味が変わる面白さがありますね。
また、雨の「しとしと」、お腹の「ペコペコ」など、音や状態を言葉で表現する「オノマトペ」も豊かです。こんなにも繊細で表現豊かな日本語、とても面白いと思いませんか?
最近では新聞やネット記事も、難しい漢字は“ひらいて”表記することが多く、本来の文字に出会う機会は減っています。
その点、小説は日本語の豊かさや奥行きを体感できる最も身近な場所なのかもしれません。
言葉に触れていると、その奥深さに感心し、時には感動します。けれど、それをどう受け取るかは人それぞれです。
私自身は「日本語って面白い」と思いましたが、同じように感じるかどうかは読む人次第。それでいいと思います。
SNSや動画が中心になった今だからこそ、ほんの少しでも「日本語に触れる時間」を持つのは悪くない。小説でも、字幕でも、方法は何でもかまいません。
自分なりの言葉との出会いがあれば、それだけで十分だと思います。
