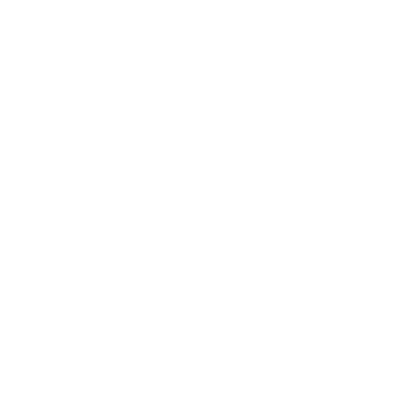私は、昔から「正解は一つじゃない」と思って生きてきた。
もちろん、学校や社会では「正しい答えは一つ」と教えられてきたし、そういう環境で育った自覚もある。
でも、どこかで「本当にそうだろうか」と疑っていた。
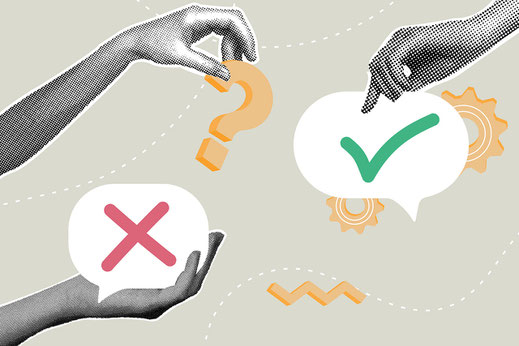
「正解探し」から「選択のデザイン」へ
私たちは長い間、効率や秩序を重んじてきた。答えが一つに決まっていたほうが、社会は整いやすいし、評価もしやすい。
でも世界は、じつは「複雑系」だ。人間の数だけ価値観があり、環境の数だけ条件がある。
農業でも飲食でも、同じように「正しいやり方」は時代や地域や人によって変わる。
AIやAGI(Artificial General Intelligence/汎用人工知能)は万能に見えるけれど、むしろ「選択肢が無限にある」という現実を私たちに突きつけてくる。
「正解」は安心、でも「多様性」は強さ
「このやり方が唯一正しい」と思えば安心だ。でも同時に、息苦しさも生まれる。
逆に「どれが正しいか分からない」と思うと不安だけど、その分、柔軟でいられる。 農業なら、大規模化が正解の地域もあれば、小規模でブランド化することが正解の地域もある。
飲食なら、ロボットが料理する店が正解の人もいれば、店主の笑顔がごちそうという人もいる。
「正解は一つじゃない」と受け止めることが、むしろ未来のサバイバルスキルになる。
「人間らしさ」の再発見
AGIがあらゆる知識や作業をこなすようになると、「機械にできないことは何か」が浮き彫りになる。
それは、正解が一つに決まらない領域だ。
たとえば価値観、感情、文化、ユーモア。
AGIに「ウケるダジャレ」を作らせても、やっぱりその場の空気を読んで笑わせるのは人間だ。
この不確かさこそが、人間の豊かさだと思う。
「正解が一つじゃない世界」を楽しむ
もちろん、私もまだ「正解が一つじゃない世界」に慣れていない。
でも、正解が一つしかないと思う世界より、はるかに面白い。 AIが畑を耕す横で、私は「どんな野菜を育てようか」と考え、ロボットが料理をつくる横で、私は「どんな会話を添えようか」と思う。
正解が一つじゃないからこそ、私たちの存在価値があるのだ。
未来への小さな宣言
これからの時代、私は「正解探し」より「意味探し」をしていこうと思う。
AIやAGIがどんなに進化しても、人間が持つ「選び方」「感じ方」「笑い方」までは、代わりにできない。
そう思うと、未来はつまらないどころか、むしろワクワクしてくる。
正解が一つじゃない世界は、混沌ではなく、自由そのものだ。